日刊鹿島アントラーズニュース
Ads by Google
2018年8月27日月曜日
◆金足農業・吉田投手、田中将大「志願の連投」……感動ハラスメントはいつまで続くのか(文春オンライン)

高校野球が「教育」だというのなら
今年の夏の甲子園では、カナノウ(金足農業)が旋風を巻き起こした。中でもエースの吉田輝星くんは決勝の大阪桐蔭戦を5回で降板するまで、秋田県予選からたった一人で10試合を完投し、甲子園では6試合で881球を投げた。心配なのは、吉田くんがきちんとしたメディカルチェックを受けているかどうかだ。
田中の登場で、球場は異様な興奮に
2013年11月3日、日本製紙クリネックススタジアム宮城。東北楽天ゴールデンイーグルス対読売ジャイアンツの日本シリーズ第7戦。3勝3敗のタイで迎えた試合は美馬学、則本昂大と繋いだ楽天が3対0で9回表を迎えた。監督の星野仙一が審判にピッチャー交代を告げ、マウンドに上がったのはエースの田中将大。
前日の試合に先発した田中は9回160球を投げ切ったが4点を失い、レギュラーシーズンからの連勝は26でストップした。160球を投げた投手は翌日、ベンチに入らないのが普通だが、「日本一」がかかった場面で星野は田中をマウンドに送った。

リーグ優勝の立役者で、すでに米メジャーリーグ、ニューヨーク・ヤンキースへの入団が決まっていた田中の登場で球場は異様な興奮に包まれた。テレビカメラが映し出すスタンドの女性ファンは、田中が投げる前からすでに涙ぐんでいる。男性ファンは「神様、田中様。巨人よ、これが僕たちのエースだ!」というプラカードを掲げる。
「田中が志願したらしいです」
田中はいつも通りのルーティーンで投球練習を終えると、最初のバッター村田修一に初球を投げ込んだ。135キロのスライダーでストライク。2球目のストレートはファールになる。149キロの球速表示が出ると解説の古田敦也が呆れた様子で言った。
「すごいなあ。すごいです。昨日160球投げた投手が150キロをコントロールできるなんて、あり得ない」
「想像を絶する疲れがあるはずですが、それを精神力が上回っている」
「普通はベンチにも入らないんですが、田中が志願したらしいです」
田中は2安打を許し、ランナー1塁3塁のピンチを招くが、最後のバッターを三振に仕留めた。仙台での「田中の15球」は伝説になった。
前日の登板で「日本一」を決められなかったエース田中が志願し、闘将星野が漢気に応えた。傍目にはそんな場面に見えたが、後日ニューヨークからテレビ出演した田中が真実を打ち明けた。
「あの時、僕は投げさせてください、と言っていません」
「田中が明日も投げると言っている」と星野に伝えていたのは楽天の二人のコーチだった。クレバーな田中は前日160球を投げた自分が、ベストのパフォーマンスを出せないこと、だから登板すべきでないことを知っていた。百戦錬磨の星野も完投した投手を連投させてはいけないことは分かっていた。
ヤンキースから楽天に「契約違反だ」と強烈なクレーム
本人が投げるつもりも、監督が投げさせるつもりもなかったのに、なぜ田中は7戦目のマウンドに上がったのか。
「満身創痍のエースが死力を振り絞る」
その場面を望んでいるファンがいるだろうと、二人のコーチは空気を読んだのである。場合によっては、田中が打ち込まれても構わない。それはそれで美談になる。球場のファンもテレビの視聴者も、あの場面で田中に非合理的な「特攻」を望んだのである。
「冗談じゃない」と怒ったのが、ヤンキース。後日、楽天に「契約違反だ」と強烈なクレームが入った。
「あわや移籍に関する契約条件の見直しに発展するところでした」
楽天関係者はそう打ち明ける。科学的に選手のコンディションを管理するメジャーでは、そもそも「160球の完投」があり得ない。それが「連投」である。わずか15球でも彼らには「バンザイ・アタック」に見えたのだ。
指導者が「虐待」で訴追されてもおかしくない
体の出来上がったプロの田中が15球投げただけでこの騒ぎである。仮に金足農業の吉田くんのメジャー入りが決まっていたら、監督の中泉一豊は球団から契約違反でクレームを入れられたことだろう。
なにせ吉田は甲子園で6試合に登板。準決勝まで全て完投で3回戦と準々決勝、準決勝と決勝が「連投」であり、決勝の5回で降板するまでわずか2週間で881球を投じているのである。米野球界の常識に鑑みれば指導者が「虐待」で訴追されてもおかしくない酷使である。にもかかわらず、中泉は決勝の後、こう語っている。
「ずっと吉田でやってきて信じていたが、できれば最後まで投げさせてやりたかった」
日本に根強く残る「散り際の美学」である。昔から不思議に思っていたのだが、スポ根漫画の金字塔『巨人の星』の星飛雄馬は、血の滲むような思いで編み出した魔球が、花形満に打たれるとマウンドにがっくり膝をつき、そのままグラウンドを去って修行に入る。
年間140試合を戦うプロ野球の世界。ホームラン1本で二軍落ちしていたら、投手が何人いても足りない。リーグ戦のレギュラーシーズンでは1年を通じて「勝ったり負けたり」を続けながら、最終的な勝率で優勝が決まる。なのに星飛雄馬は一発打たれたら、「僕の負けだ」といちいち絶望するのだ。
『葉隠』の「武士道というは死ぬことと見つけたり」なのか、『戦陣訓』の「生きて虜囚の辱めを受けず」なのか。日本人は「勝ったり負けたり」のリーグ戦より「負けたら終わり」のトーナメントを好む。その刹那に命を燃やしきる若者を「美しい」と感じる。881球で完全燃焼し、甲子園のベンチ前に跪いてシューズ袋に土を詰める吉田くんがたまらなく好きなのだ。
吉田くんの肩の筋肉はどうなっていたか
しかし、前回も書いたように少年サッカーの指導に関わる筆者はこう思うのだ。
「おいおい吉田くん、そんなことをしている暇があったら、肩のアイシングしなよ。これで終わりじゃないんだから」
881球を投げ「下半身が動かないから変えてくれ」と直訴した吉田くんを、アイシングもさせず外野の守備に回したときには卒倒しそうになった。前日からの球数を考えれば、吉田くんの腕の毛細血管は切れて、肩の筋肉は炎症を起こしていた可能性が高い。その選手をそのまま外野に立たせた。2番手投手が打ち込まれたり、あるいは味方打線の奮起で競った展開になったりしたら、もう一度、彼をマウンドに立たせるつもりだったのだろうか。

「後のない緊張感が生徒を育てる」という指導者も
「負けたら終わり」のトーナメントには独特の緊張感があり、見ている方はたまらない。「後のない緊張感が生徒を育てる」という指導者もいる。しかし、春夏の甲子園を軸にトーナメント一辺倒で運営される高校野球は「特攻」「玉砕」を生みやすい。吉田くんをはじめとするカナノウの「雑草軍団」には「ここで終わっても構わない」という悲壮感が漂っていた。
「全員がプロになるわけではないのだから、完全燃焼させてあげたい」という専門家もいる。しかし18歳の若者に「完全燃焼」を求めているのは指導者であり、主催者であり、観客である。人生100年の時代、18歳で一旦燃え尽きた若者は、その後の82年間をどう過ごすのだろう。

高校野球が「教育」だというのなら、指導者や主催者はそこまで考えるべきではないだろうか。二度とボールが投げられない体になったり、二度と野球などしたくない気持ちになったりした選手を「野球でここまで頑張れたのだから、残りの人生もきっと頑張れる」と放り出すのが教育だろうか。
一発勝負のインターハイや選手権より「大きな試合」
大会運営の改革が進んでいるのが高校サッカーだ。
夏の甲子園より一足早く始まったサッカーの高校総体(インターハイ)。千葉県大会の準決勝で全国大会の常連、流通経済大学付属柏高校は習志野高校に1対2で敗れた。怪我から復帰したばかりのキャプテン、関川郁万くんは試合終了のホイッスルがなると、ニコニコしながら習志野高校の選手の肩を叩いた。
決して「緩い」わけではない。プロや日本代表、海外のクラブチームを目指す彼らには、一発勝負のインターハイや選手権より「大きな試合」があるのだ。2011年に始まった「高円宮杯JFA U-18サッカープレミアリーグ」である。
プレミアは2011年に始まったU-18世代最高峰のリーグ戦で、高校チームとJリーグのユースチームが東西に別れ、ホーム&アウェイで年間18試合を戦う。彼らにとってはこのリーグが「世代最強チーム」を決める戦いの舞台だ。プロのスカウトも運に左右されにくいリーグ戦で、選手の実力をじっくり見極められる。
一発勝負はスポーツ本来の「楽しさ」を奪いがち
世代別日本代表の常連でもある流経大柏の関川くんの場合、5月には鹿島アントラーズから内定が出ていた。インターハイでは怪我の状態も考えつつの「安全運転」。流経大柏の監督が無理な使い方をしたら、アントラーズから「ちょっと待ってくれ」とクレームがつくだろう。まして若い選手を育ててトップチームに上げることが使命のJユースの指導者にとって、「特攻」「玉砕」はご法度だ。優勝しても選手を壊してしまったら「何をやってるんだ」と大目玉を食らう。
高校サッカーの場合、プレミアの下には「プリンスリーグ」があり1部、2部、3部、4部と続く。同じレベルのチームが勝ったり負けたりを繰り返し、好成績を収めれば上のカテゴリーに上がれる。したがって野球のコールドゲームのような一方的な試合は少ない。
負けられないトーナメントにも面白さはあるが、「特攻」「玉砕」の戦いは指導者や選手に過度のプレッシャーを与え、スポーツ本来の「楽しさ」を奪いがちだ。悲壮感を漂わせた高校生を炎天下の過密日程で戦わせる「夏の甲子園」。この感動ハラスメントが続く限り、科学的、物資的な不利を精神力で補おうとする日本の悪癖は治りそうにない。
|
|
Ads by Google
日刊鹿島
- 1
 ★2024年11月の記事まとめ(日刊鹿島アントラーズニュース)2024-11-02
★2024年11月の記事まとめ(日刊鹿島アントラーズニュース)2024-11-02 - 5
 ★2025年02月の記事まとめ(日刊鹿島アントラーズニュース)2025-01-31
★2025年02月の記事まとめ(日刊鹿島アントラーズニュース)2025-01-31 - 7
 ◆【サッカーコラム】好調の佐野海舟 それでも代表復帰は望み薄(サンスポ)2024-10-23
◆【サッカーコラム】好調の佐野海舟 それでも代表復帰は望み薄(サンスポ)2024-10-23 - 9
 ◆明治安田J1第37節 鹿島快勝 C大阪に2-0(茨城新聞)2024-11-30
◆明治安田J1第37節 鹿島快勝 C大阪に2-0(茨城新聞)2024-11-30 - 24
 ★2025年03月の記事まとめ(日刊鹿島アントラーズニュース)2025-02-28
★2025年03月の記事まとめ(日刊鹿島アントラーズニュース)2025-02-28 - 38
 ◆[プレミアリーグEAST]鹿島アントラーズユース登録メンバー(ゲキサカ)2025-04-03
◆[プレミアリーグEAST]鹿島アントラーズユース登録メンバー(ゲキサカ)2025-04-03 - 67
 ◆J1鹿島 熱い歓迎感謝 キャンプ地、宮崎入り(茨城新聞)2025-01-14
◆J1鹿島 熱い歓迎感謝 キャンプ地、宮崎入り(茨城新聞)2025-01-14 - 86
 ★2024年10月の記事まとめ(日刊鹿島アントラーズニュース)2024-10-06
★2024年10月の記事まとめ(日刊鹿島アントラーズニュース)2024-10-06 - 90
 ◆【鬼木・鹿島は2025年J1開幕・湘南戦をどう戦う?】(サッカー批評)2025-02-12
◆【鬼木・鹿島は2025年J1開幕・湘南戦をどう戦う?】(サッカー批評)2025-02-12 - 99
 ◆《2025鹿島宮崎キャンプ》J1鹿島 練習試合に向けて調整(茨城新聞)2025-01-20
◆《2025鹿島宮崎キャンプ》J1鹿島 練習試合に向けて調整(茨城新聞)2025-01-20
過去の記事
- ► 2024 (1133)
- ► 2023 (1261)
- ► 2022 (1152)
- ► 2021 (1136)
- ► 2020 (1404)
- ► 2019 (2168)
-
▼
2018
(2557)
-
▼
8月
(194)
-
▼
8月 27
(7)
- ◆金足農業・吉田投手、田中将大「志願の連投」……感動ハラスメントはいつまで続くのか(文春オンライン)
- ◆植田が2戦ぶり先発のセルクル・ブルージュ、10人のアントワープに敗れて今季初黒星(ゲキサカ)
- ◆豊川雄太が決勝弾の起点! オイペンは今季初白星で最下位を脱出(ゲキサカ)
- ◆大迫勇也、開幕戦で不発も好感触「一気に結果を出せそうな感覚ある」(サッカーキング)
- ◆日本代表GK動けず…鳥栖FW金崎が“黄金コンビプレー”から移籍後初ゴール!!(ゲキサカ)
- ◆鹿島安西PK献上「いじられた」ACLで雪辱だ(ニッカン)
- ◆手倉森氏だけでなく…衝撃20年来の敏腕コーチ斬り 足を引っ張る技術委員会(zakzak)
-
▼
8月 27
(7)
-
▼
8月
(194)
- ► 2017 (2892)
- ► 2016 (2193)
- ► 2015 (1859)
- ► 2014 (2464)

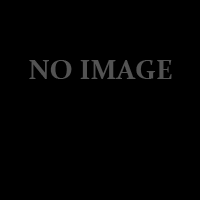
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/025c87f7.c69da211.03b500ad.d0208622/?me_id=1213310&item_id=17636238&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7893%2F9784847047893.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7893%2F9784847047893.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)